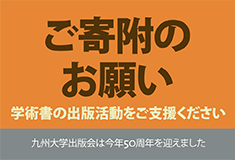
お勧めBOOKS
九州大学出版会
〒819-0385
福岡県福岡市西区元岡744
九州大学パブリック4号館302号室
電話:092-836-8256
FAX:092-836-8236
E-mail : info@kup.or.jp
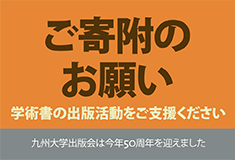
〒819-0385
福岡県福岡市西区元岡744
九州大学パブリック4号館302号室
電話:092-836-8256
FAX:092-836-8236
E-mail : info@kup.or.jp