目次
はじめに
序論 漱石とカントの反転光学
第一節 漱石のカント研究
第二節 経験的実在論にして超越論的観念論
第三節 実在観念の世界反転光学
第四節 文芸の批判哲学的視座
第五節 西田と漱石の根本差異
第六節 批判光学の実存論的意義
第 I 部 漱石、晩年の心境
第一章 明暗双双 漱石の世界反転光学
第一節 作者の死と世界大戦
第二節 同時代哲学批評
第三節 最後の夏の手紙
第四節 禅語「明暗双双」の意義
第五節 老子との批判的対話
第六節 小宮豊隆の『明暗』解説
第二章 間テクスト的な漱石の読解
第一節 晩年の創作家の態度
第二節 明暗双双の反転光学
第三節 則天去私の詩学
第四節 漱石というテクストを読む
第五節 『三四郎』からの本格始動
第六節 カントの言語論的な理性批判
第三章 近代小説家の道草
第一節 『明暗』執筆の日常
第二節 自由・自然・自動の詩学
第三節 我執主題化の方途
第四節 『道草』の方法論的課題
第五節 自伝的三人称小説の始まり
第六節 遠い場所からの帰還
第七節 近代小説家の道草
第四章 『道草』テクストの遠いまなざし
第一節 迂回するテクストの語り
第二節 世界の実在感の喪失
第三節 『猫』と『道草』の語り
第四節 『道草』の相対叙法
第 II 部 漱石、帰還の実相
第五章 健三と漱石の帰還
第一節 『道草』の帰還の視座
第二節 健三の帰還と制作の始動
第三節 漱石帰還の実相
第四節 漱石壮年の本格始動
第五節 テクストの余裕の視座へ
第六節 大乗的と世間的の相互返照
第七節 職業作家漱石の始動
第六章 微笑する語りの視座 天然自然の論理
第一節 『硝子戸の中』末尾の微笑
第二節 人生の事実性へのまなざし
第三節 微笑の視座の公的開放性
第四節 漱石文学における自然
第五節 漱石の自然の詩学
第六節 『道草』の自然の論理
第七節 『道草』テクストの微笑
第七章 「神」から「天」へ
第一節 神の眼という言葉
第二節 『道草』の神と自然
第三節 天に禱る時の誠
第四節 神なき時代の自己の道徳
第五節 西洋的絶対神への違和
第六節 神の眼から天の視座へ
第七節 天命としての文学の語り
第八章 真の厭世文学の公道
第一節 漱石の孤独と厭世
第二節 生死をめぐる公的省察
第三節 真の厭世文学の理念
第四節 形而上の厭世からの生還
第五節 生老病死の継続の詩学
第六節 厭世耐忍の論理
第 III 部 現象即実在の反転光学
第九章 『行人』一郎の絶対と『道草』以後
第一節 自然を我が師とす
第二節 生死一貫の根本命題
第三節 死後の魂という難関
第四節 神は自己だ、僕は絶対だ
第五節 絶対をめぐる省察の経歴
第六節 「塵労」対話篇の生成
第十章 生死の超越から生死一貫へ 近代心霊主義批判
第一節 宗教哲学的な主題設定
第二節 一郎論理の空転の根
第三節 近代心霊主義の影
第四節 縹緲玄黄外。死生交謝時。
第五節 漱石の心霊主義批判
第六節 ジェイムズとの批判的対話
第七節 心霊主義との訣別
第十一章 「現象即実在、相対即絶対」の批判光学
第一節 宗教への問いの鍛錬
第二節 「塵労」テクストの反転
第三節 絶対即相対から相対即絶対へ
第四節 現象即実在の批判哲学
第五節 漱石文学のリアリズムの道
第六節 徹底的に批判的な経験的実在論
第七節 経験的実在界の明暗反転光学
第十二章 心機一転の文学の道
第一節 芸術制作上の個と普遍
第二節 死・狂気・宗教
第三節 宗教への哲学的な問い
第四節 漱石の禅語使用
第五節 経験の大地への帰還
第六節 心機一転の光学の視座
結論 漱石文芸の根本視座
第一節 批判的な近代の文学の道へ
第二節 形而上学的唯心論との格闘
第三節 『点頭録』の世界反転光学
第四節 明暗双双の往還光学の道
参考文献
あとがき
索引

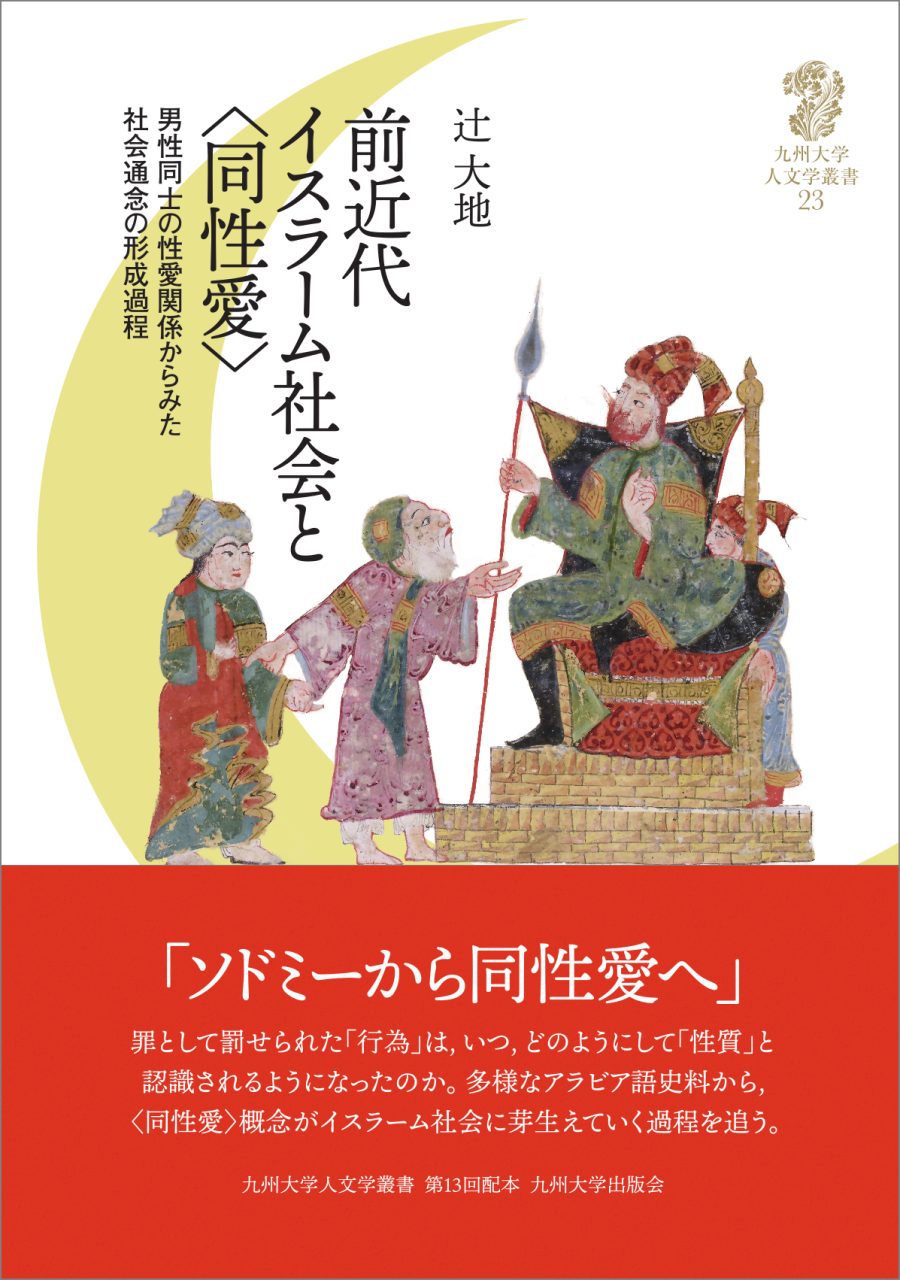
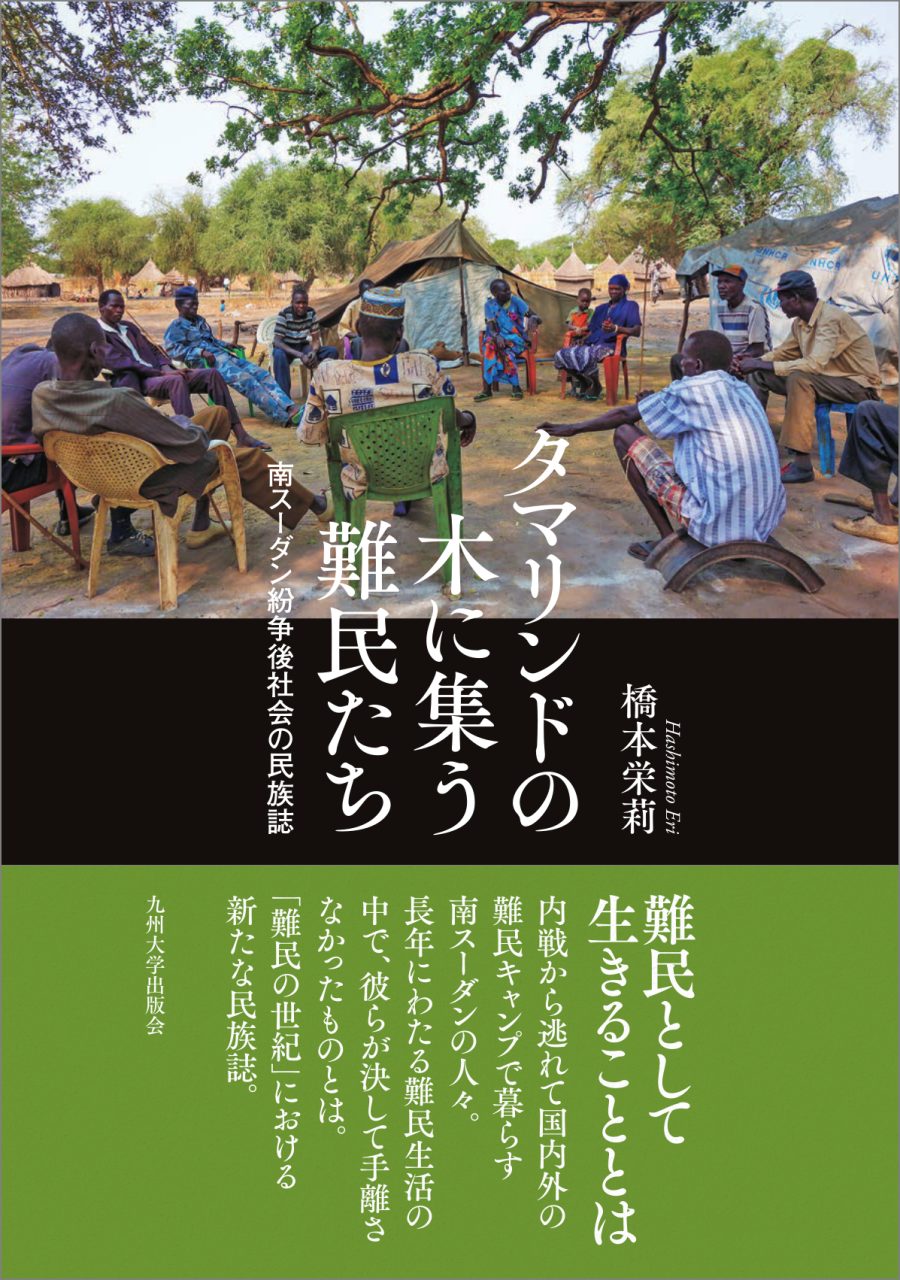
![液体ロケットの構造システム設計[改訂版]](https://kup.or.jp/wp-content/uploads/2023/09/4e94ffb64b992b62fa1fd7b0c45e4efe-902x1280.jpg)