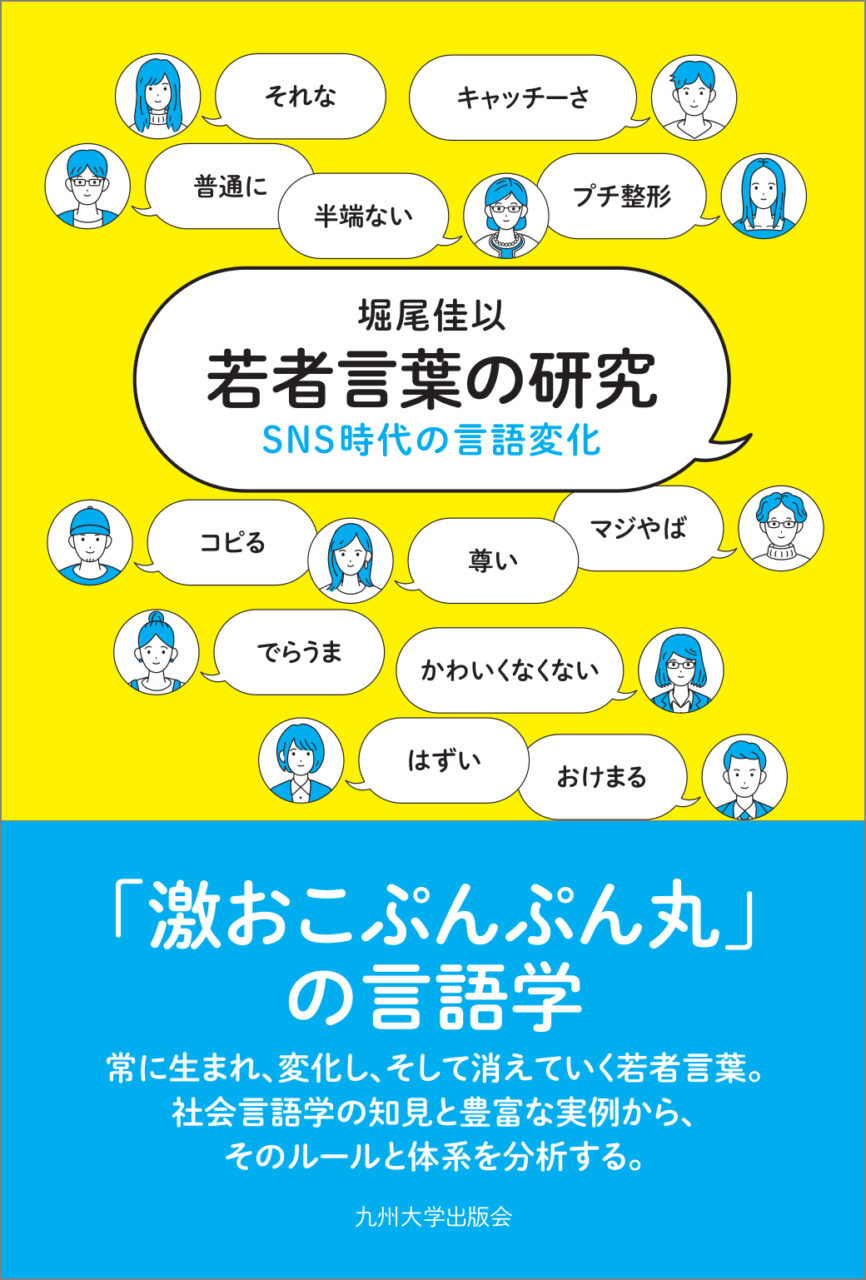社会科学
アジアの英知と自然
- 定価 1,320円(税率10%時の消費税相当額を含む)
今や全世界へ影響を及ぼしているアジアの文化遺産の中から薬用植物をとりあげ,歴史的背景,植物学的認識,著者の研究結果等を交えて,医薬学的問題点などを分かり易く解説する。 (さらに…)

金融サービスにおける消費者保護
- 定価 4,620円(税率10%時の消費税相当額を含む)
英国では,2000年金融サービス市場法が成立し,金融サービス機構(FSA)による監督という新しいパラダイムへと移行しつつある。本書は,英国における銀行・証券・保険・消費者信用等,金融サービスの提供に関連した消費者保護の問題を幅広く取り扱っている。また,グローバリゼーションの進展を考慮して,欧州共同体の影響を適切に概観している。わが国の金融サービス法のあり方を考える上で,本書は大いに示唆に富んでいる。 (さらに…)

ミクロ経済分析
- 定価 3,630円(税率10%時の消費税相当額を含む)
ゲーム理論を援用することにより,不完全競争市場および市場の失敗についての評価をおこなう。非対称情報複占繰り返しゲームの逐次的均衡における信念列の構成問題や,ナッシュ均衡の精緻化を射程にいれたBalanced Temptation Equilibrium の分析とともに,労働市場における交渉ゲームの均衡分析とその応用分析が多方向から展開されている。 (さらに…)

構造変化と金融・経済
- 定価 3,080円(税率10%時の消費税相当額を含む)
複雑かつ多様化する現代の経済について,特にその構造変化を整合的かつ総合的に捉えることを目指した論集。実証的な調査・検証に加え,制度的な分析や計量分析・理論モデル分析も含む多様な手法により,多面的にアプローチする。 (さらに…)

国際会社法論集
- 定価 5,500円(税率10%時の消費税相当額を含む)
商法「外国会社」規定の研究から国際会社法の体系化を目指す。内国会社法に対応する国際会社法を中核としながら,周辺の法分野の考察を行う。国際会社法研究をライフワークとする著者の論文集。 (さらに…)

企業破綻と金融破綻
- 定価 7,700円(税率10%時の消費税相当額を含む)
明治後期・大正前期の鉄道企業破綻(第1部)と大正バブル期に急拡大して破綻した銀行・生保(第2部)の20余の事例を総括し,破綻と破綻をつなぐ「負の連鎖」と,経営者の投機的行動を誘発促進させた扇動者等を摘出して「リスク増幅のメカニズム」を解析した。 (さらに…)

政策分析2001
- 定価 3,960円(税率10%時の消費税相当額を含む)
『政策分析2000』に続く政策評価研究会による研究成果の第2集。比較政策論の観点から,欧米各国・地域での政策動向を丹念に検証し,その政策的含意を明らかにすることによって,21世紀日本における政策的課題と政策形成のための新たな指針の獲得を目指す。 (さらに…)

技術革新と経済構造
- 定価 4,180円(税率10%時の消費税相当額を含む)
「企業の研究開発投資」,「新技術・新製品の普及」,「市場の構造」,「技術構造と経済構造」をキーワードとして,技術革新と経済構造に関する分析をミクロ経済学的視点とマクロ経済学的視点の両面より行う。 (さらに…)

中華人民共和国教育法に関する研究
- 定価 8,250円(税率10%時の消費税相当額を含む)
本書は,近年中国で制定された中華人民共和国教育法を対象として,現代中国の教育法規と教育法現象を解明した本格的な研究の書である。社会主義的教育法の変容を中心に現代の中国の教育法の法体系と法理論,そして教育社会の法現象の特徴を明らかとする。 (さらに…)

旧韓国〜朝鮮の日本人教員
- 〔品 切〕(参考:本体価格 7,500円)
日本人が旧韓国―植民地朝鮮の教育界を牛耳っていたことは事実であるが,日本人教員の具体的な人事や教育活動を総体として把握することは困難である。そこで本書では,便宜的な方法としてふたつの方向からの接近を試みた。彼ら日本人教員の出身県と出身校からのアプローチである。 第1部は,西日本各県(山口・福岡・佐賀・熊本・鹿児島・沖縄)出身者の動きを追跡したものである。 第2部は,戦前日本の高等師範学校4校と旧韓国―植民地朝鮮との関わりを追求したもので,第I部を県人会版とすれば,第II部は高師同窓会版である。 ...

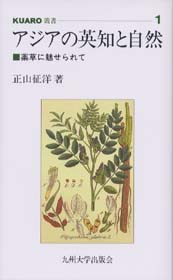
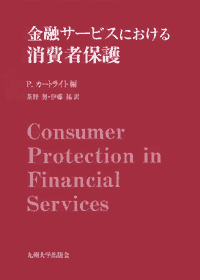
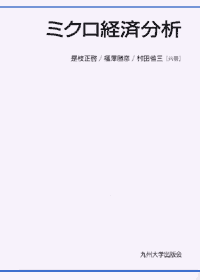

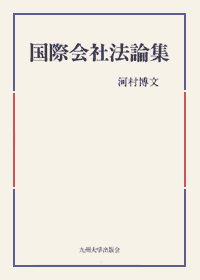
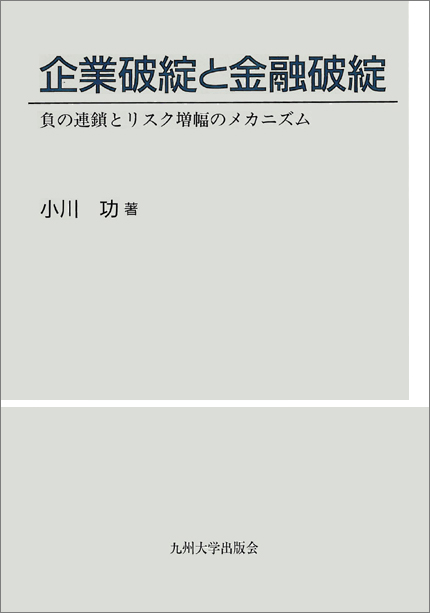
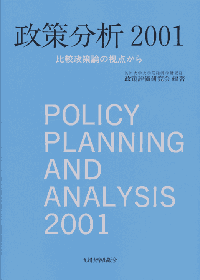
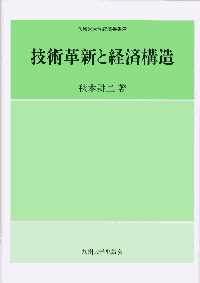
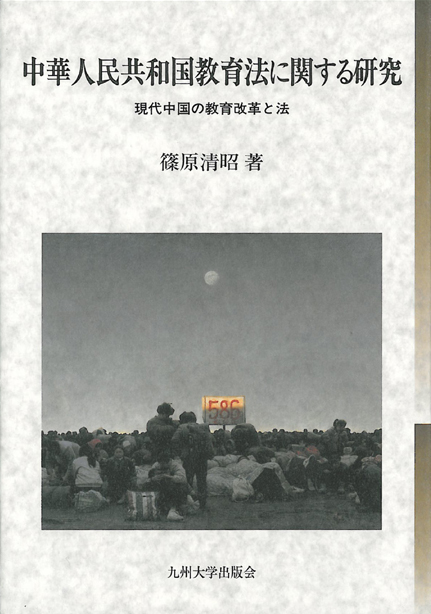
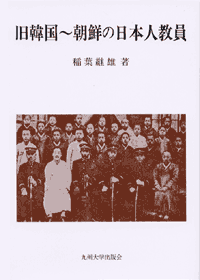
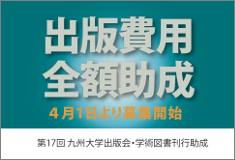
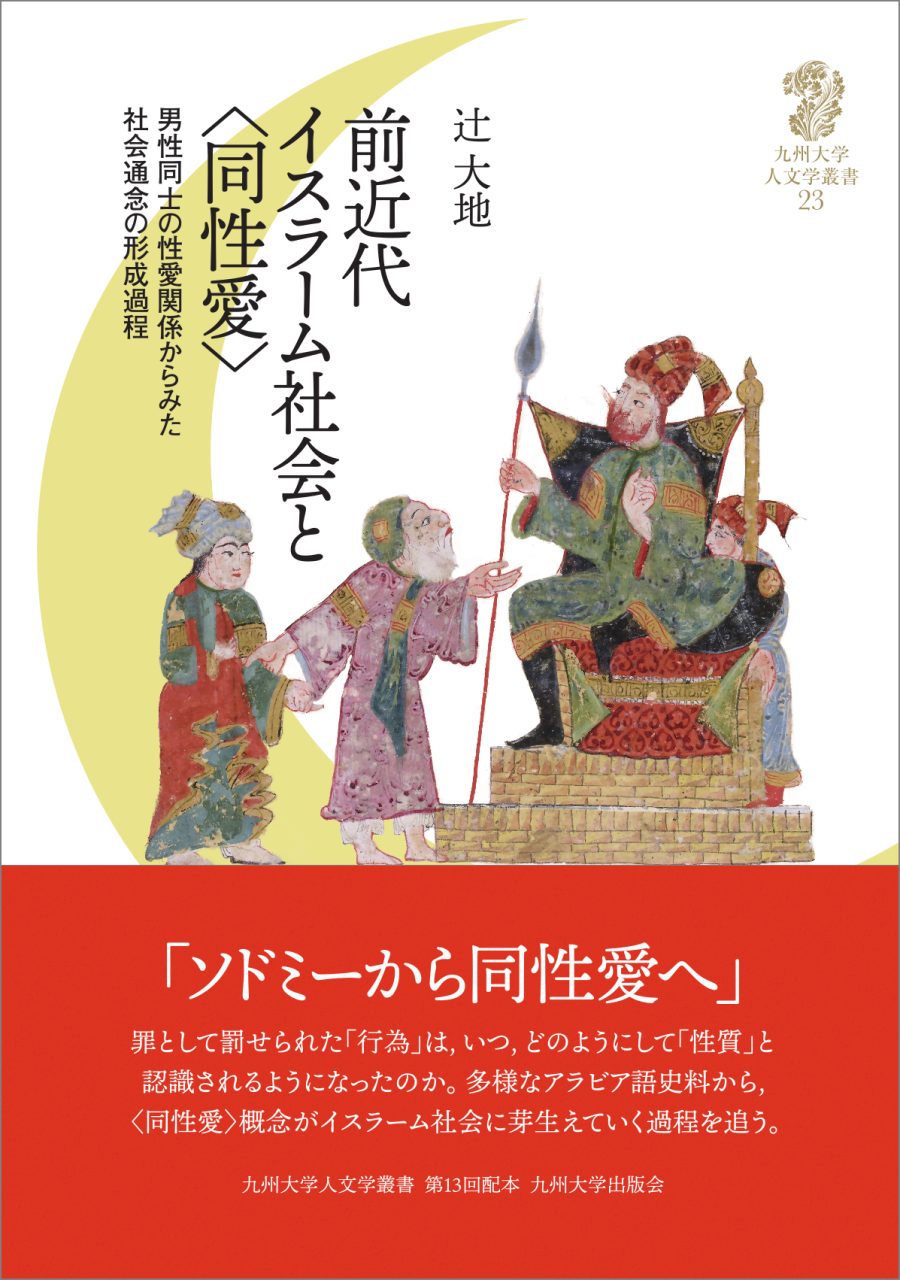
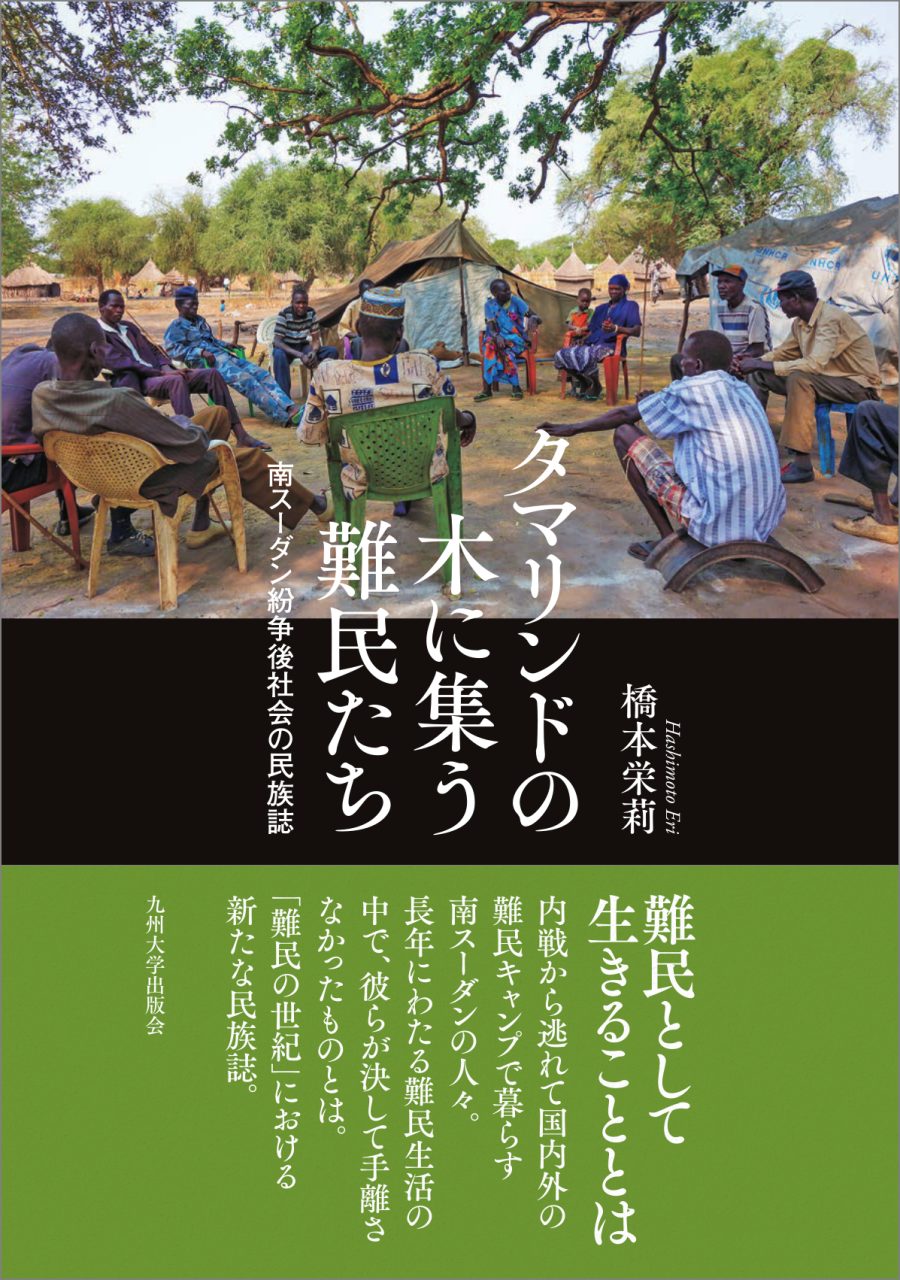
![液体ロケットの構造システム設計[改訂版]](https://kup.or.jp/wp-content/uploads/2023/09/4e94ffb64b992b62fa1fd7b0c45e4efe-902x1280.jpg)