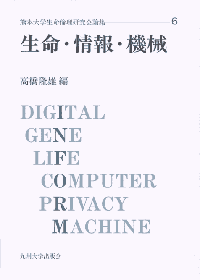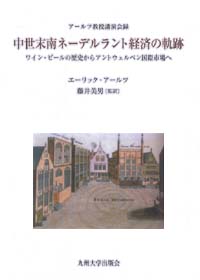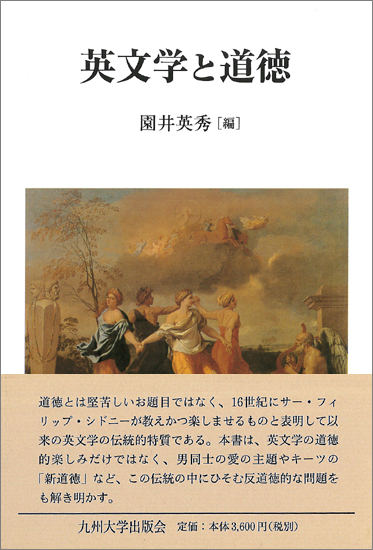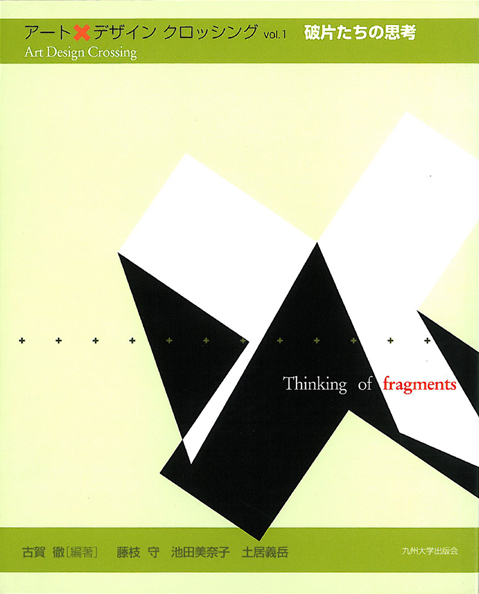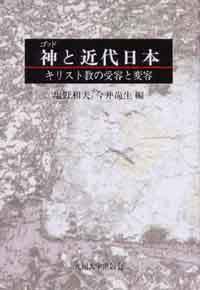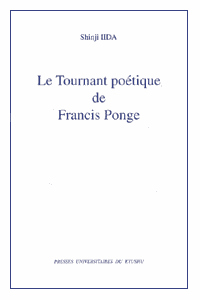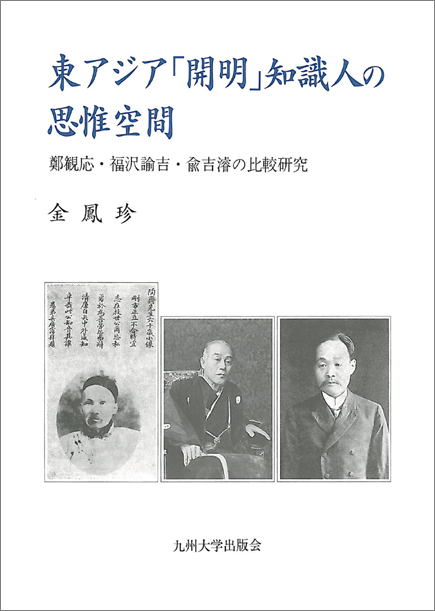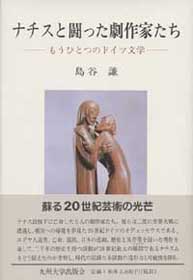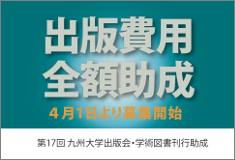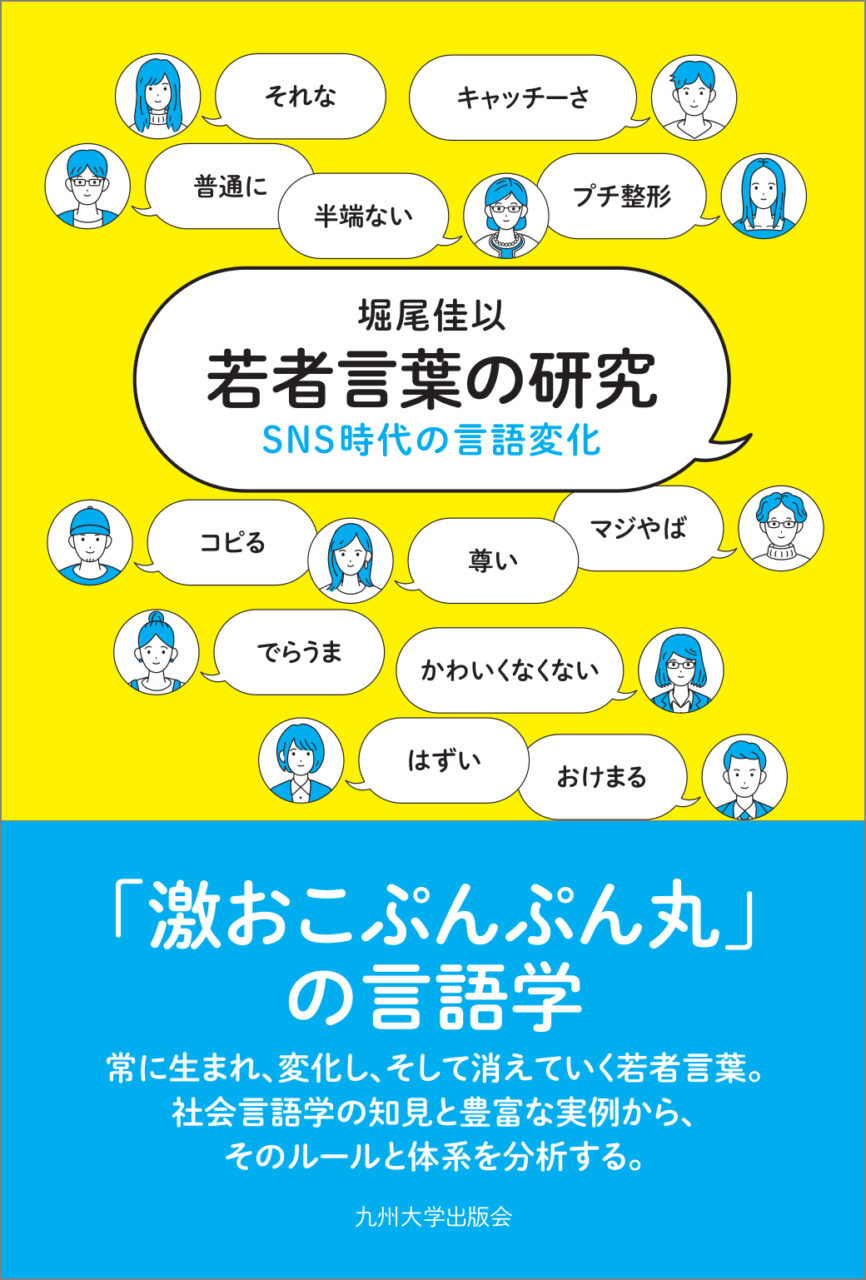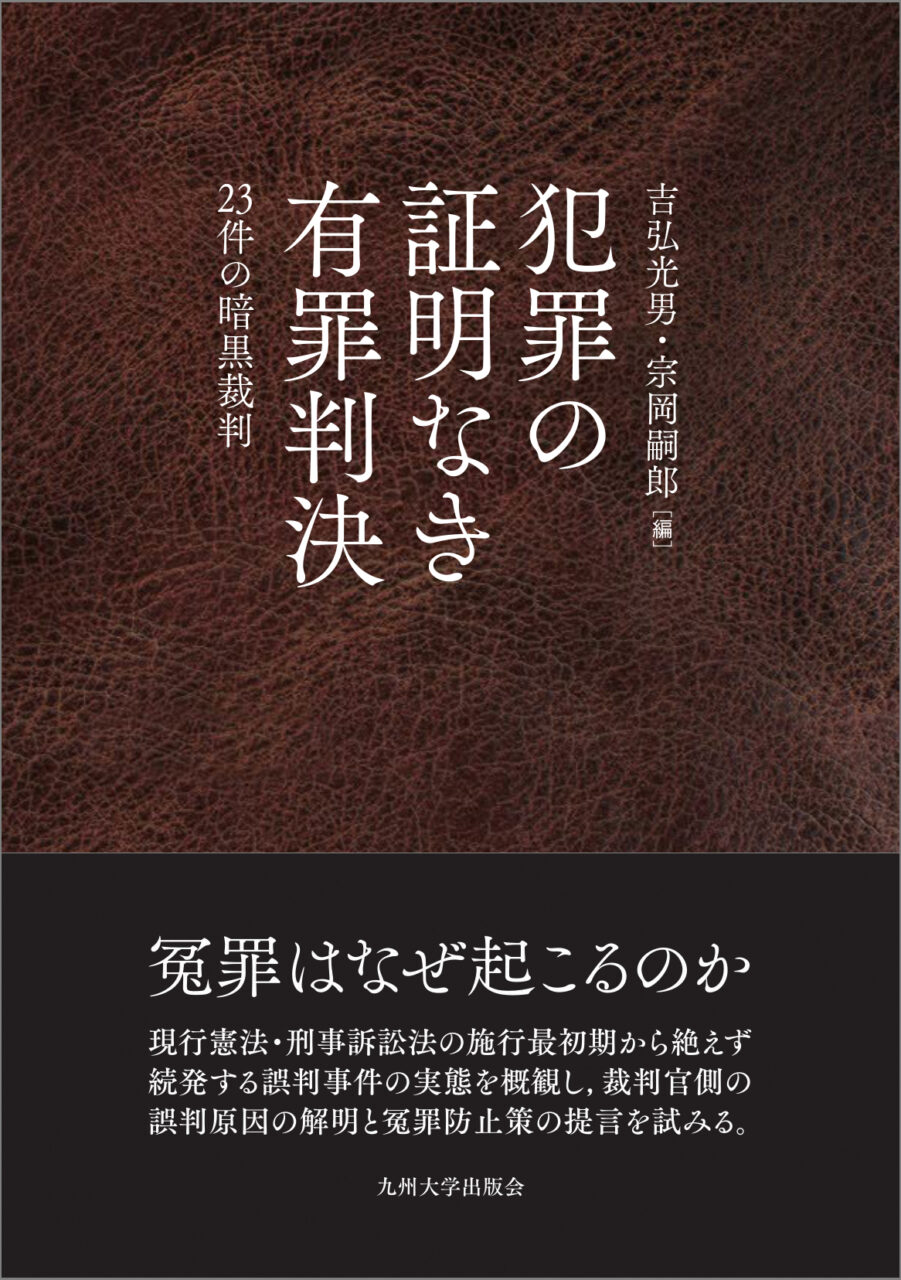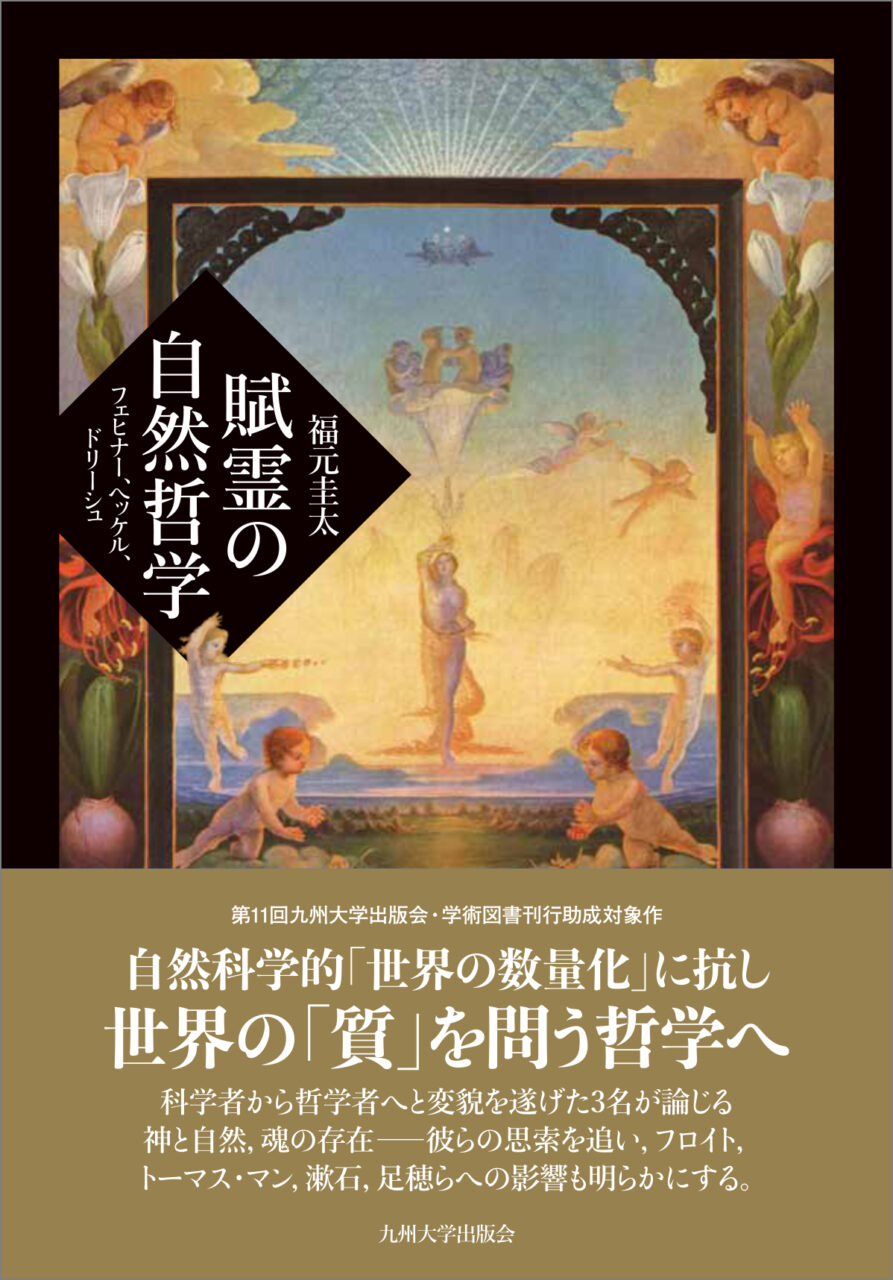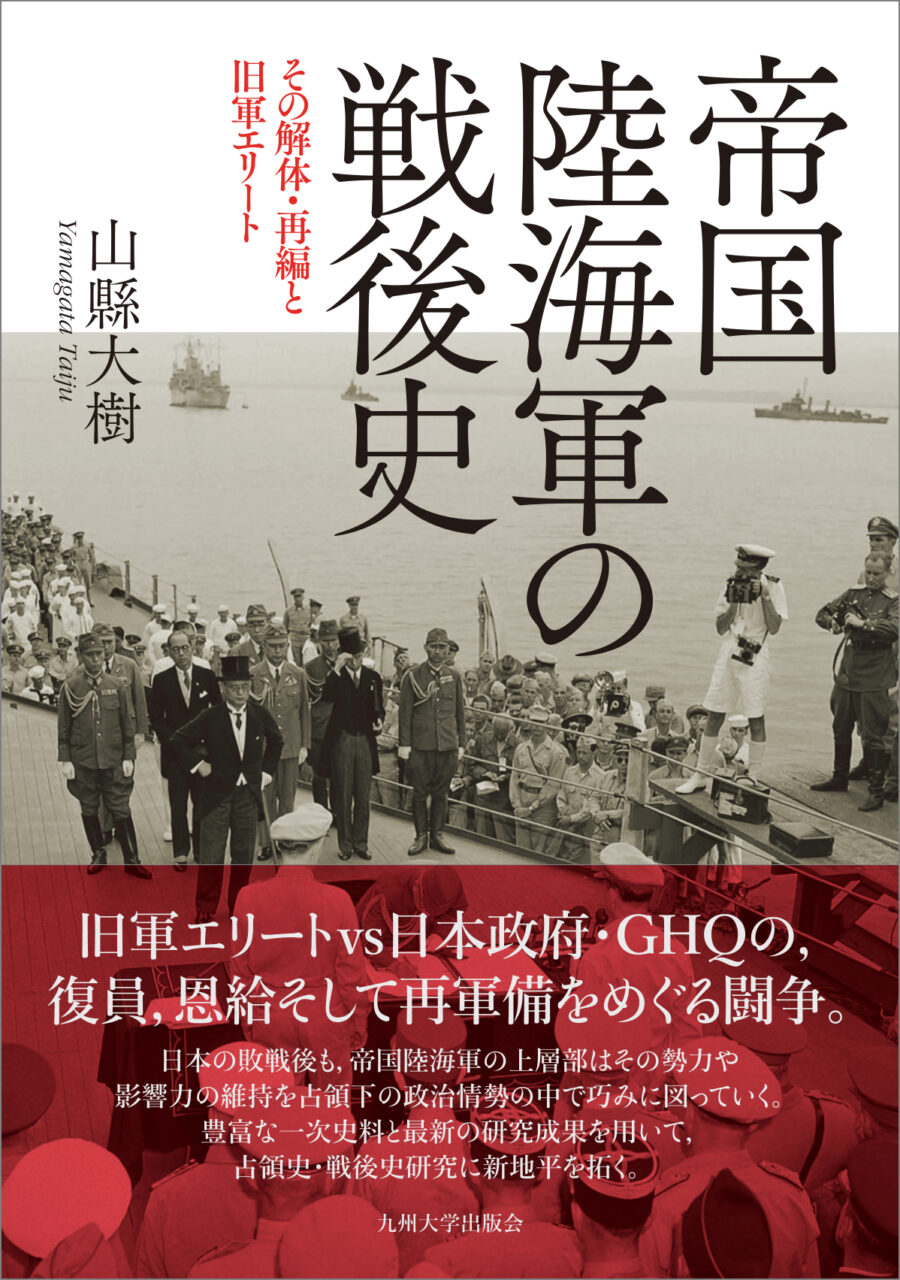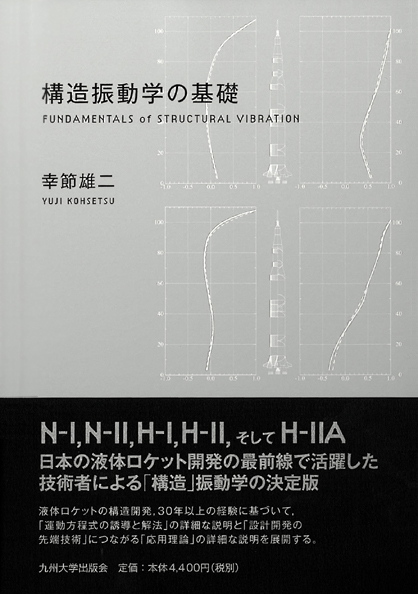人文科学
生命・情報・機械
- 定価 3,080円(税率10%時の消費税相当額を含む)
生命倫理研究とは,現実の諸問題の本質を解明するとともに,問題解決に向けての具体的指針を模索するものである。それには倫理学をその任に堪えうるように鍛え上げることと多くの分野にわたる共同作業が不可欠である。本論集は日常的な共同研究を基礎にして,徹底した討議をへて成った論文集である。「情報」を中心テーマとする本書では,医療情報や遺伝子情報をめぐる倫理的諸問題はもとより,情報環境と人間,機械と生命との根本的関係や人間の尊厳のあり方の考察を通じて,生命と情報に関する本質的な問題が論じられている。「遺伝子」...

中世末南ネーデルラント経済の軌跡
- 定価 1,650円(税率10%時の消費税相当額を含む)
レウヴェン大学E.アールツ教授による連続講演会の邦訳集。中世初期から後期にかけてヨーロッパのビールとワインの嗜好変化をたどり,ホップビールの流行とワイン消費の減退,セルヴォワーズ(エール)の遍在を検証することで,飲料の価格動向の重要性を示す。次に,資本主義揺籃の地ブリュッヘとアントウェルペンに焦点を当て,ヨーロッパ金融市場の変遷を説く。前者はイタリアの為替技術を伝承しそれを西欧全域に伝播する役割を果たしたが,そこから重心移動した後者の金融市場では手形の裏書など新技術を切り開いたことを強調する。さ...

哲学的人間学序説
- 定価 4,180円(税率10%時の消費税相当額を含む)
哲学的人間学の主題は,人間の「人格」である。観念論哲学によれば,人格は理性的な定立作用のうちにあり,実存哲学によれば想像力的な投企作用のうちにある。これら二つの主体性は,互いに異質的であり,さしあたり対立的関係のうちにあるが,その具体的かつ暫定的(不完全)な統一が人間の身体である。定立作用は「外側から見た身体」(ケルパー)を拠点としており,投企作用は「内側から見た身体」(ライプ)を拠点としている。しかし単独な人間身体(ライプケルパー)は,決して両者の完全な統一ではなく,いわゆる人間的矛盾をはらん...

英文学と道徳
- 定価 3,960円(税率10%時の消費税相当額を含む)
道徳とは堅苦しいお題目ではなく,16世紀にサー・フィリップ・シドニーが教えかつ楽しませるものと表明して以来の英文学の伝統的特質である。本書は,英文学の道徳的楽しみだけではなく,男同士の愛の主題やキーツの「新道徳」など,この伝統の中にひそむ反道徳的な問題をも解き明かす。 (さらに…)

アート・デザイン・クロッシング vol.1
- 定価 2,200円(税率10%時の消費税相当額を含む)
本書は,画廊の一画に設けられた「アート・オープン・カフェ」に於いて,4名の研究者が一般の参加者とともに行った討論の模様を収録したものである。作曲家の藤枝守,哲学者の古賀徹,現代デザインの池田美奈子,西洋建築史の土居義岳がそれぞれ主題を提起し,モダニズムのあとの世界,アメリカという問題,主体の喪失と透明化,文化資本主義と身体,テクストの解体,生活世界と専門知といった観点から議論を行った。 (さらに…)

神(ゴッド)と近代日本
- 定価 2,640円(税率10%時の消費税相当額を含む)
日本の近代化は,社会の各層における根本的な変容をその内容とする。本書は,欧米キリスト教文化の受容を多様な分野において検討することによって,近代日本の内実を重層的に解き明かすことを目的とするものである。 (さらに…)

Le Tournant poétique de Francis Ponge
- 定価 10,120円(税率10%時の消費税相当額を含む)
1938年―1948年はフランシス・ポンジュの詩学にとり,きわめて重要かつ豊穣な時代である。事実,出世作『物の味方』以降,彼の詩学はこの時代に決定的な変貌をとげようとしていた。本書は,この時代に執筆された詩作品だけでなく,講演,評論,書簡,草稿等の多様なテクスト群に詳細な分析を行いながら,新たなポンジュ詩学の多彩な可能性を明快に描き出した意欲作である。 (さらに…)

SART
- 定価 2,200円(税率10%時の消費税相当額を含む)
SART(主動型リラクセイション療法)は、動作法の臨床実践の積み重ねから誕生し、からだの動きとリラクセイションにより自分の再発見と可能性を探るアプローチである。一般の人たちの心身の不調の改善にも役立ち、障害を持つ人たちやこころとからだに問題をもつ人たちに広く適用できる心理療法である。 (さらに…)

東アジア「開明」知識人の思惟空間
- 定価 6,380円(税率10%時の消費税相当額を含む)
本書は,東アジア三国――清国,日本,朝鮮――の「開国」により,伝統的な東アジア地域秩序と近代的な欧米国際秩序が接触した近代という大転換期の,それぞれの知識人――鄭観応,福沢諭吉,兪吉濬――の対内外観とその変容を比較分析したものである。この比較分析のための支柱として「アジアから考える」という視点および文明論的な視点を提示し,彼らの対内外観を「構造相関」的に分析した。本書は,近代東アジアの比較政治思想史の研究における新しい地平を開くことを目指している。 (さらに…)

ナチスと闘った劇作家たち
- 定価 3,960円(税率10%時の消費税相当額を含む)
ナチス政権下に亡命した五人の劇作家たち。彼らは二度の世界大戦に遭遇し,祖国への帰還を夢見た20世紀ドイツのオデュッセウスである。ユダヤ人迫害,亡命,抵抗,日本の悲劇,歴史と実存等を描いた秀作を通して,二千年の歴史をもつ演劇が二十世紀最大の難問(アポリア)であるナチズムをどう捉えたのか考察し,時代の記録たる演劇の造形力と可能性を探る。 (さらに…)